はじめに:独学でも宅建士は合格できる
「宅建士に独学で挑戦して、本当に受かるのか?」
これは、僕自身が宅建の勉強を始めたときに最も感じていた不安でした。
しかし結果として、僕は46点という得点で一発合格を果たすことができました。
もちろん、決して楽な道ではありません。でも、正しい順序と習慣を積み上げていけば、誰でも到達できるラインだと思っています。
この記事では、僕が実際に行った「宅建士に独学で合格するための勉強法」を、リアルな体験談とともにお届けします。
・宅建士に興味はあるが、何から始めればいいか分からない初心者の人
・仕事や学校で忙しいけれど、スキマ時間を使って宅建士合格を目指したい人
・独学で宅建士試験に挑戦したいが、教材選びや勉強方法に不安を感じている人
第1章:なぜ独学を選んだのか
僕が宅建士を目指したのは、会社から資格取得を勧められたことがきっかけでした。
不動産事業をいくつも行う会社だったので、むしろ取るのが当たり前の状況でした。
ですが、僕にはスクールに通う時間も、通信講座に回すお金もなかったため、独学一択という状況。
地方から上京したばかりで、本当に日々の生活費を捻出することに手いっぱいな日々、
「やる気ゼロから始めて、仕事後の1時間だけでなんとか合格したい」
そんな思いで手探りしながら進めていったのが、今回紹介する勉強法です。
第2章:実際に行った3ステップの勉強法
① テキストを3周読む|目的は“全体像の把握”
僕がまず取り組んだのは、市販の宅建テキストを3周読むこと。
大丈夫です。流し読みで構いません。決して深入りすべきステップではなく、
この段階の目的は「正答を出すこと」ではなく、宅建士という試験の全体像を頭に入れることでした。
参考書の章末問題で、正答率が低くてもなんら問題はありません。
「これは法律系の問題だな」「この用語は民法でよく出るな」といった感覚をつかむことが、後に続くアウトプット学習の土台になります。
② 過去問を5周以上解く|問題慣れと反復が鍵
本格的な実力をつけるステップが、過去問演習の反復です。
最初に過去問に挑んだとき、僕は正直鉛筆を転がして答えを選ぶレベルでした。
3周目に入ってもわからない問題は山ほどありました。
でも、大切なのは「できなかったこと」に向き合うこと。
正解・不正解にかかわらず、解説を読み込み、テキストと照らし合わせて理解する。
これを毎回繰り返すことで、少しずつ知識が繋がっていきました。
5回、6回と繰り返すうちに、宅建士試験特有の“問題のクセ”や“ひねり方”にも慣れてきます。
これがいわゆる「問題慣れ」。宅建はマークシート式ですが、慣れなしでは本番で得点は伸びません。
③ 模試を3回実施|本番感覚で弱点をあぶり出す
最後に取り組んだのが、模擬試験形式の演習を3回。
これは試験1か月前から行いました。
講座を受講するのには何十万必要ですが、模試だけの受験であれば、1万円から無料まで色んな模試が行われています。
模試の目的は、過去問では測れない「本番力」を鍛えることです。
得点できなかった箇所を分析し、苦手分野を再確認。ここでの気づきが本番での安心感につながりました。
第3章:宅建士に合格するために最も大切なこと
合格の最大要因は、間違いなく「問題慣れ」です。
何度も問題を解き、出題のパターンや意図を体に染み込ませる。
マークシート式の試験でも、知識の深さと応用力が問われる以上、「なんとなくでも答えられる」ような状態になるまでの繰り返しが必要です。
第4章:この手法は二級建築士にも通用した
この勉強法は、実は二級建築士の学科試験でも応用し、僕は一発合格しています。
インプット(テキスト)→アウトプット(過去問)→総仕上げ(模試)というフローは、知識系資格全般に有効です。
おわりに:独学でも最短合格は可能。戦略と継続がカギ
時間がない、やる気がない、環境が整っていない——
そんな人でも、正しい手順と反復で宅建士は独学合格できます。
僕のやり方がすべての人に最適とは限りませんが、
「どうやって勉強を始めたらいいかわからない」「合格者のリアルを知りたい」という方には、
きっと役に立つはずです。
宅建士の独学に挑むあなたの背中を、少しでも押せたらうれしいです。
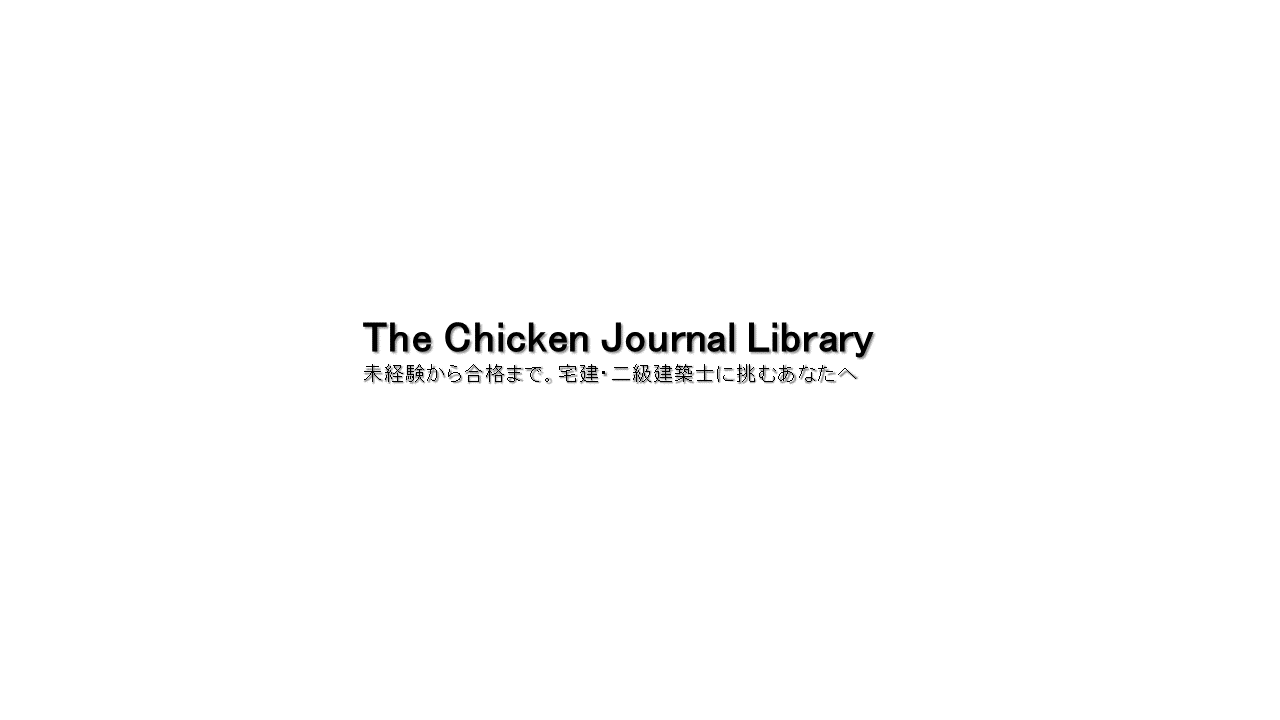
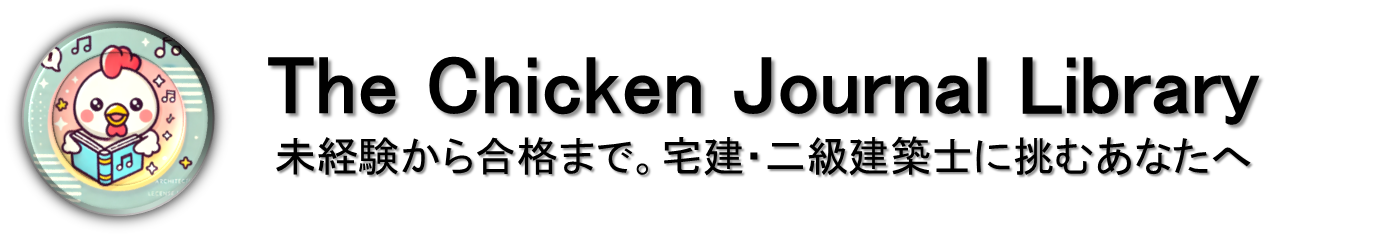
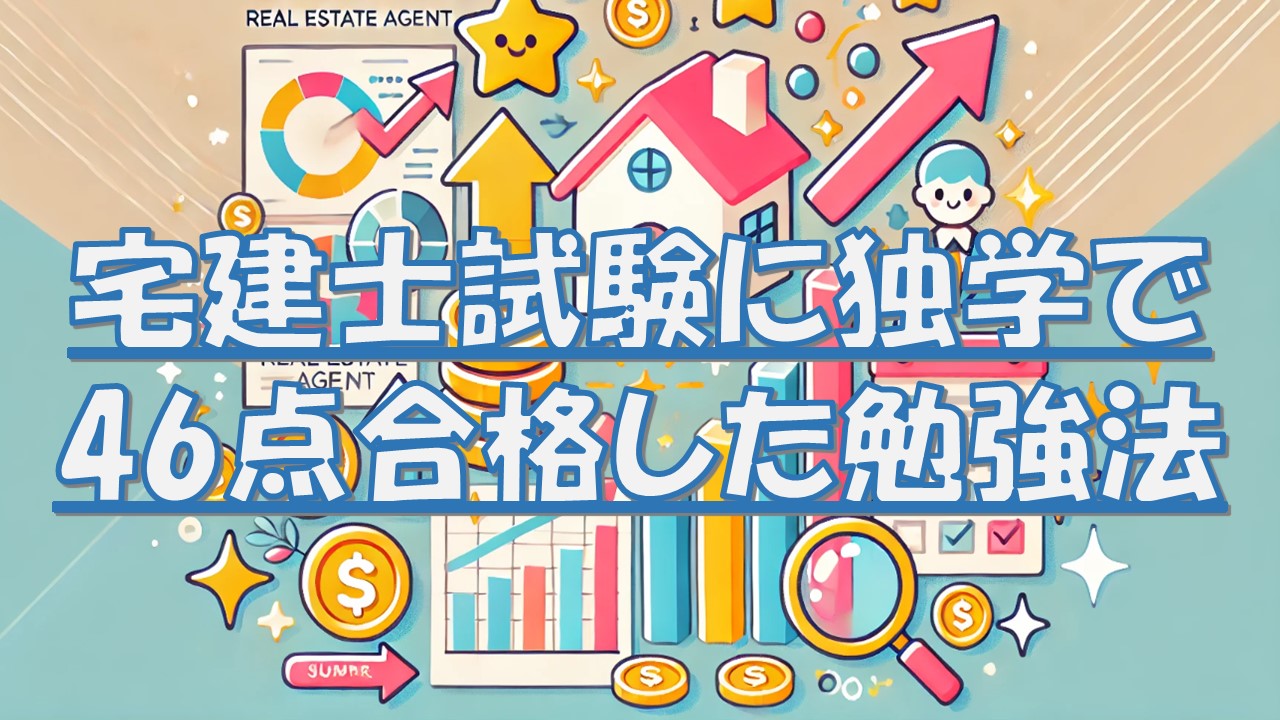
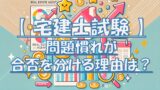


コメント