はじめに
宅建士試験の合格率は毎年15~17%前後。
この数字だけを見ると「やっぱり難しいのかも…」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
ですが実際には、しっかりと準備をして本気で取り組んでいる人にとって、宅建士試験は決して高い壁ではありません。
私の受験当時、周りの先輩方でもまじめに取り組んだ人達の多くは合格しており、落ちてしまう人の多くは、合格には程遠い点数だったことを記憶しています。
この記事では、合格率が低く見えるカラクリや、宅建士試験の実際の難易度について、リアルな視点から解説していきます。
・宅建士試験の難易度や合格率について詳しく知りたい人
・これから宅建士試験の勉強を始めようと考えている人
・効率的な勉強法や合格のためのポイントを探している人
宅建士試験の合格率の実態
過去の合格率の推移
宅建士試験の合格率は毎年おおよそ15~17%で推移しています。
以下は、直近の合格率の推移です。
| 試験年度 | 合格率 |
|---|---|
| 令和5年 | 17.2% |
| 令和4年 | 17.0% |
| 令和3年 | 17.9% |
| 令和2年 | 13.1%(12月実施) |
| 令和2年 | 17.6%(10月実施) |
一見すると「国家資格らしい難しさ」を感じますが、実はこの数字にはある“からくり”があるのです。
合格率が低く見える理由
宅建士試験には、受験資格がありません。
つまり「誰でも受験できる」ため、対策を十分にしないまま、「とりあえず受けてみる」という受験者も多く含まれています。
その結果、全体の合格率は15~17%にとどまっているのです。
しかし、試験対策をきちんと行った層だけに絞れば、合格率は40〜50%以上に跳ね上がるというデータもあるほどです。
ただ宅建士試験は出題範囲が非常に広く、「権利関係」や「宅建業法」、「法令上の制限、「税その他」の科目に分かれた試験内容が網羅されています。
やみくもに勉強をしても合格ラインの36点前後に届く可能性は低いので、ご注意ください。
宅建士試験の難易度は本当に高いのか?
他の資格試験との比較
宅建士試験と他の国家資格の合格率を比較してみましょう。
| 資格名 | 合格率(平均) |
|---|---|
| 宅建士 | 約15~17% |
| 行政書士 | 約8~15% |
| 司法書士 | 約4~5% |
| 社会保険労務士 | 約6~7% |
こうしてみると、宅建士試験は国家資格の中では比較的合格しやすい試験であることが分かります。
合格者の特徴
合格者に共通するのは、次のような特徴です。
- 過去問を繰り返し解いた
- 「暗記」ではなく「理解」を意識していた
一方で、「何となく」で臨んでしまうと、合格は遠のいてしまいます。
裏を返せば、明確な目的と計画さえあれば、誰でも合格を目指せる資格とも言えます。
本気で挑戦すれば合格できる理由
計画的な学習と過去問の活用
宅建士試験で合格を勝ち取るためには、反復学習と問題慣れがカギになります。
特に重要なのが「過去問」です。
過去問を最低10年分、各5回以上繰り返すこと。
問題に慣れてくると、「この選択肢のパターン、見たことあるな」と瞬時に判断できるようになります。
5回繰り返した以降は過去問の解答から答え合わせまでの流れはが30分前後で行えるようになります。何度も何度もやって体に過去問をしみこませることが大切です。
これはまさに、経験値のなせる業です。
最終月の模試の役割
学習の最終段階では、過去問だけでなく模試にも取り組みましょう。
模試では新作の問題や、少しひねった設問に触れることができ、自分の理解の死角をあぶり出すことができます。
特に法改正がされた部分に関しては、模試を通じて理解をしていく必要があります。
辛い努力は必要ありません。
必要なのは、プレッシャーを弾き返す継続力と反復です。
合格スケジュール(3カ月バージョン)
以下は、3カ月で合格を狙うためのシンプルなスケジュール例です。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 1ヶ月目 | インプット学習(テキスト精読+動画講義)+過去問着手(2年分) |
| 2ヶ月目 | 過去問演習(5年分×反復)+苦手分野の補強 |
| 3ヶ月目 | 過去問演習(10年分×繰り返し)+模試×2~3回+見直し |
このペースで進めれば、3カ月でも十分に合格を狙えます。
大切なことは問題慣れすることです。
まとめ
宅建士試験の合格率が低く見えるのは、「とりあえず受けてみる人」が多いためです。
本気で対策をした人だけに絞れば、実は宅建士試験は現実的な目標であることが分かります。
宅建士の合格は、特別な才能やセンスではなく、正しい方法と継続的な努力で手に入るものです。
もし今、「自分にできるかな…」と感じている方がいれば、安心してください。
正しい手順を踏めば、あなたも合格ラインに到達できます。
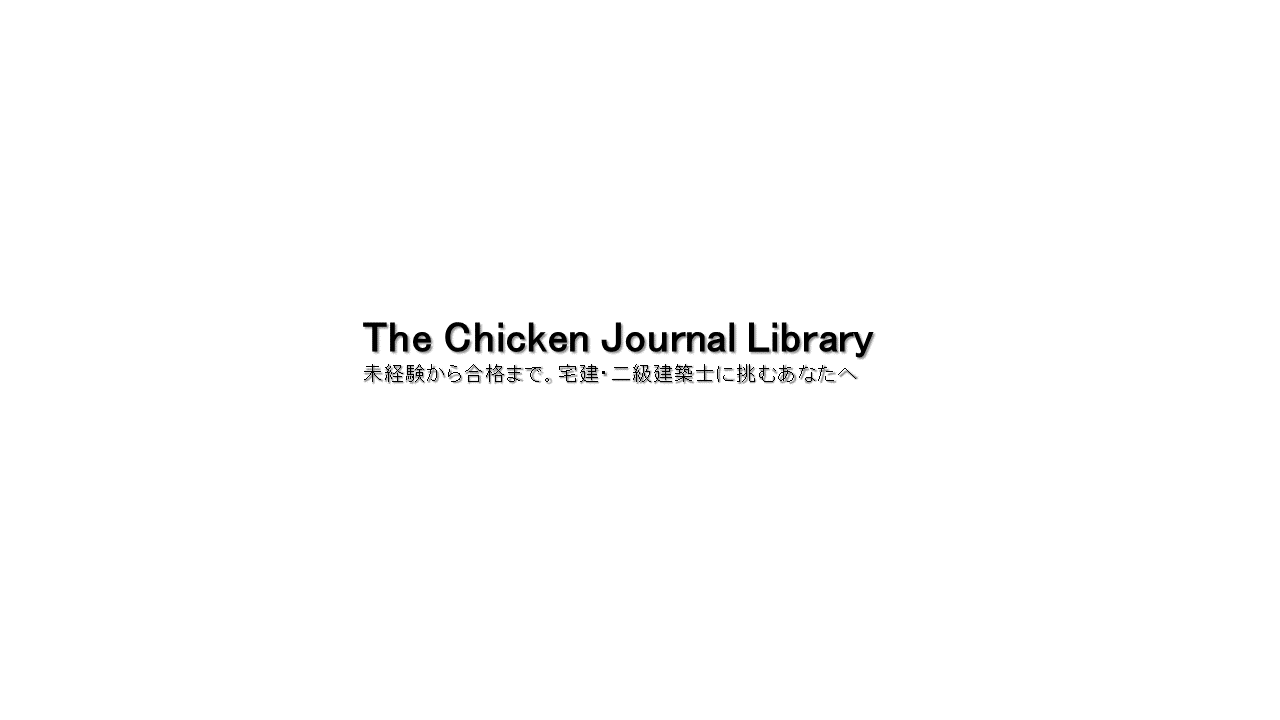
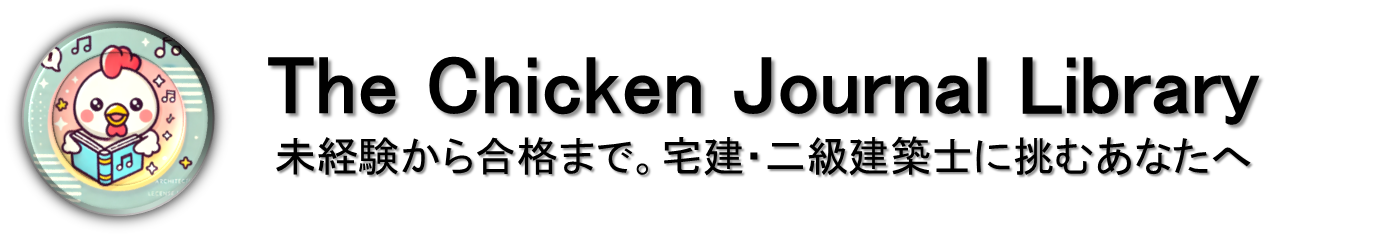
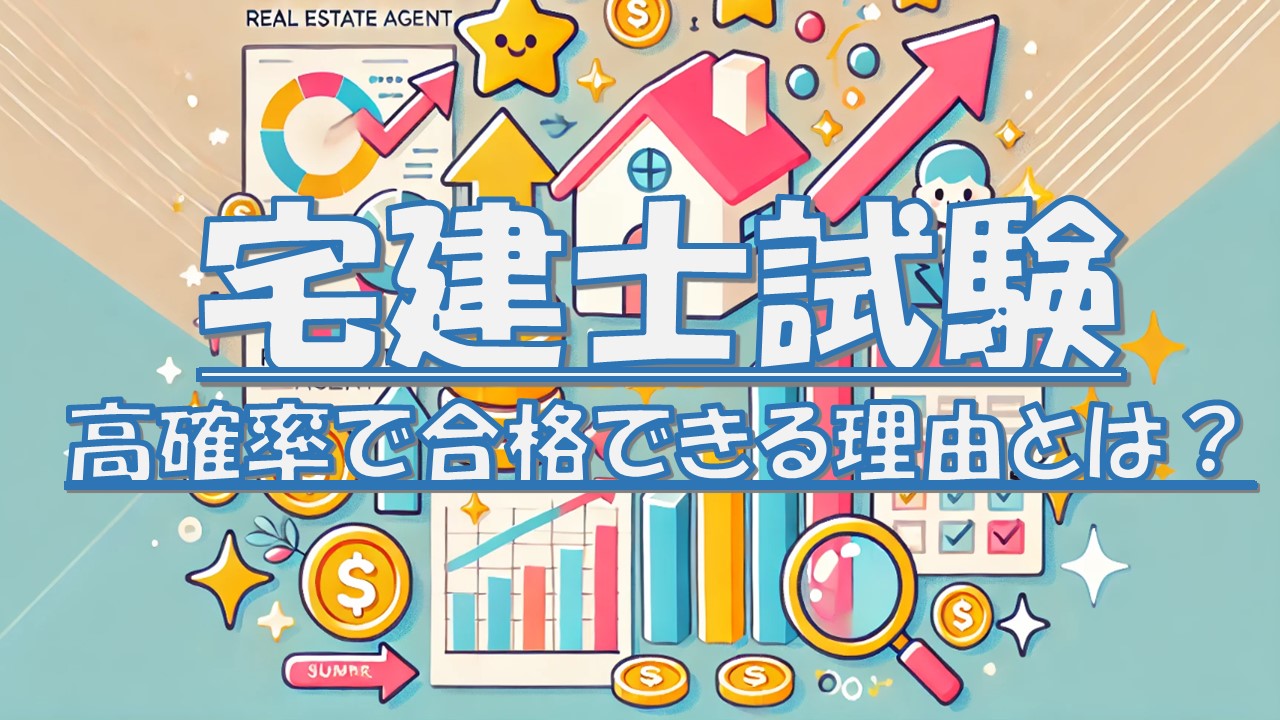

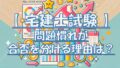
コメント