当記事ではあくまで「合格するため」という所に軸を置いて記事を書いています。
宅建士を目指す方にとって、「どれくらい勉強すれば合格できるのか?」という疑問は、今のライフスタイルや仕事を維持しつつ、勉強を両立していくための大切な指標になりますよね。
筆者のチキンは宅建士に合格するために必要なのは勉強期間ではなく、問題慣れが重要だという結論付けています。
実際、仕事や家庭と両立しながら合格を目指す方も多いため、無理のないスケジュール設計が合格への重要なカギになります。
この記事では、合格するために必ず必要な勉強時間を解説します!
・宅建士試験の勉強時間がどれくらい必要か知りたい初心者
・忙しくても合格できる現実的なスケジュールを知りたい人
・モチベーションを維持しながら勉強を継続したい人
宅建士合格に必要な勉強時間の目安は?
初心者の場合の標準勉強時間
筆者の考える宅建士合格に必要な勉強時間の目安は、ざっと300〜400時間です。
特に、民法や法令上の制限は初学者には難易度が高く、理解に時間がかかるため、ある程度まとまった勉強時間が必要とされます。
勉強時間のうち約200~300時間を3~5カ月程度で行い、
試験1か月前に約100時間取り組むことが合格を確実につかみ取るスケジュール感です。
また、宅建士試験は「暗記だけ」では突破できません。
過去問演習を通じて、知識の応用力や問題慣れを養うことも重要なため、時間に余裕を持って計画を立てましょう。
社会人・主婦など、ライフスタイル別の勉強時間イメージ
仕事や家事で忙しい中でも、日々コツコツ積み上げれば合格は十分可能です。以下は一例です。
- 社会人(フルタイム勤務)
平日1時間+休日3時間 → 週に約10時間 - 主婦・パート勤務の方
平日2時間+休日2時間 → 週に約14時間
目安として、1日1〜2時間を確保し、最後の1か月は1日3時間で追込仕上げを頑張れば、6カ月程度で合格ラインに到達可能です。
宅建士の試験は出題範囲が広く、「問題慣れ」をしておく必要があります。
最後の1か月では限りなく「問題慣れ」状態にしておくことが大切です。
📌【ポイント】
宅建士の試験は原則として毎年10月の第3日曜日に実施されます。
春先(3月〜4月)から少しずつ準備を始めると、無理のないペースで完成度を高めることがおすすめ!
初心者向け!合格までの勉強スケジュール例
試験日から逆算したスケジュール設計
- 6カ月前〜4カ月前
→ 参考書を1周し、全体像をつかむ - 4カ月前〜2カ月前
→ 過去問演習と解説理解に集中 - 2カ月前〜試験直前
→ 模試や予想問題を解き、弱点を潰す
ステップ別時間配分の考え方(前回記事と連携)
合格への王道は、以下の配分を意識することです。
- ステップ① 全体像把握:20%
(参考書を通読して全体をざっくり理解) - ステップ② 過去問攻略:60%
(問題演習→解説確認→知識定着を徹底) - ステップ③ 模試・復習:20%
(総仕上げとして本試験レベルの演習)
過去問対策に6割の時間を充てることで、出題傾向に慣れ、本番でも落ち着いて問題に臨めるようになります!
忙しい人が勉強時間を確保するためのコツ
私自身、ディベロッパー勤務時代に宅建士試験に挑戦しましたが、
フルタイム勤務+残業がある生活でも、移動時間や行き帰りの電車の中でアプリを使って問題演習を積み重ねることで、勉強時間を確保していました。
「まとまった時間が取れないから無理」と諦めず、スキマ時間の積み上げが合格への近道です!
スキマ時間の活用法
- 朝の通勤電車→アプリで5問だけ解く
- 昼休み→参考書を10分読む
- 夜寝る前→その日学んだことを軽く復習
1回5〜10分でも、1日に何度も学習を挟むことで、記憶に定着しやすくなります。
勉強を習慣化させるテクニック
- 「時間を作る」のではなく「行動を固定化」する
(例:電車に乗ったらアプリを開く、歯磨き後に参考書を読む) - モチベーションに頼らない
やる気が出るのを待つのではなく、「時間がきたら機械的に始める」仕組みを作りましょう!
📖【おすすめ書籍】
時間のある方には、
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』もぜひ読んでみてください。
小さな行動を積み上げる重要性が、実践的に学べます!
【まとめ】
宅建士試験は、正しい時間管理とスケジュール設計さえできれば、初心者でも十分に合格可能な資格です。
大切なのは、「無理なく続けられる自分なりの勉強スタイル」を早く確立すること。
今日からできる一歩を踏み出して、コツコツ積み上げていきましょう!
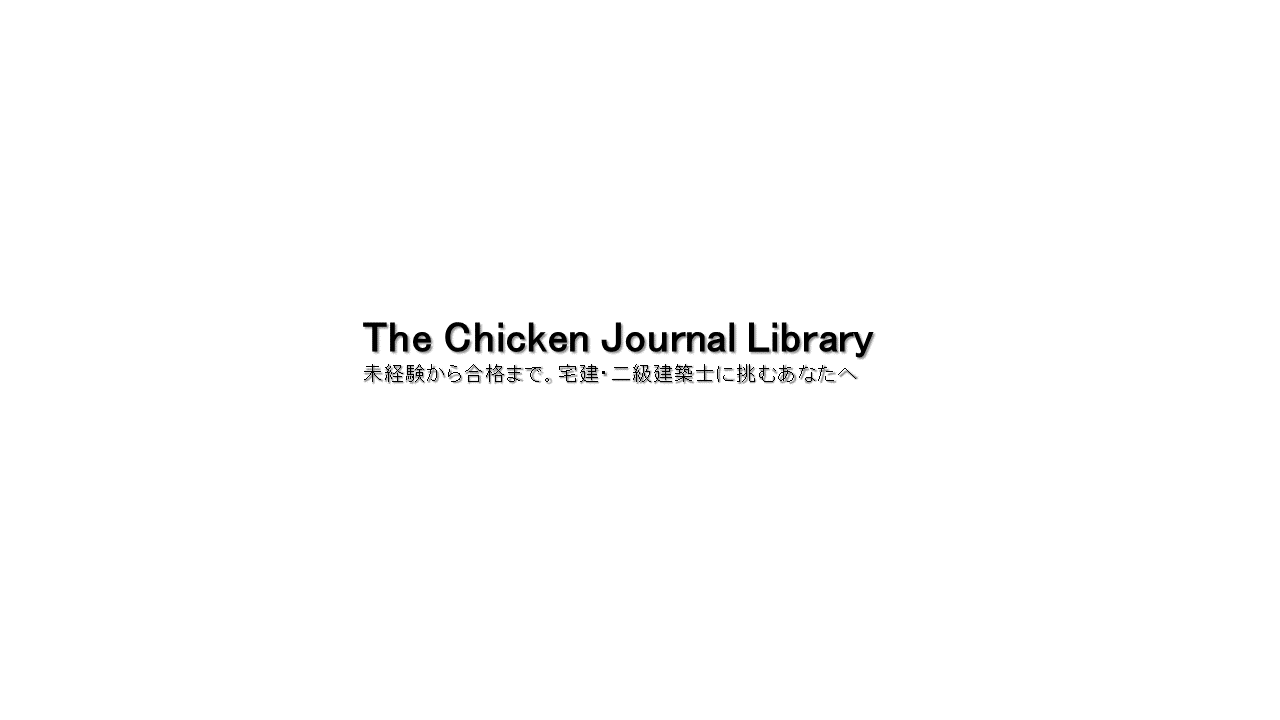
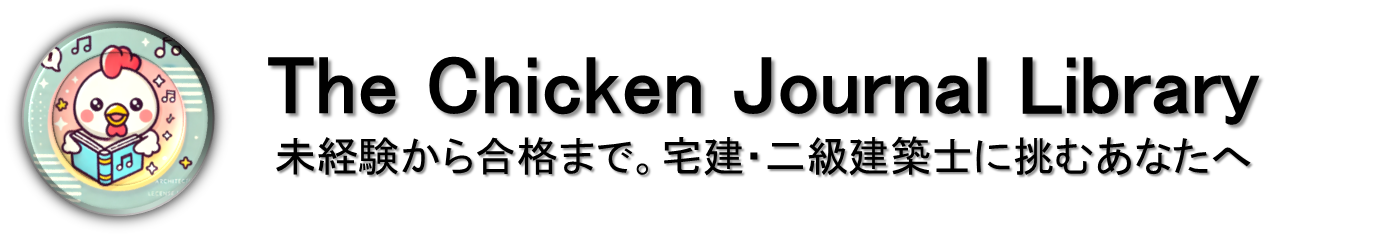




コメント